●1985年(昭和60年)文芸同人誌『文海』第10号発表 カット・嘉藤千香子
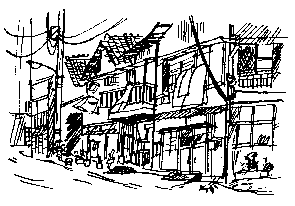 新車で買って半年もたたない朱鴛男(ときお)のバイクだったが、また調子がわるい。 新車で買って半年もたたない朱鴛男(ときお)のバイクだったが、また調子がわるい。
アパートの前庭にとめておいたらエンジンの真下の小砂利にオイルが黒くしみている。こないだ点検整備してもらったぱかりなのに、なおっていないのだ。排気量350CC、ヨーロピアンスタイルのメタリックな黒。50万をキャッシュではらっていた。
さすがに頭へきて、サーピス工場ヘカリカリになった声で電話をいれる。
受話器をとった女事務員は朱鷺男の声を覚えているので、またかという調子に、おざなりに、すいませんねえといった。相手は、環状7号線沿いにあるサービス工場の事務室で、ポテトチップのバケットをゆうゆうと空ッポにしながら応対する女なのだ。
アパートのむかいにある米屋の公衆電話にむかっていた朱鷺男は、音をたてて受話器をおいた。すると、足もとに集って米つぶをひろっていた雀たちがいっせいに飛びあがった。
その翌朝のこと。バイク工場さしまわしのサーピス員が、8時半びったしにアパートのドアをたたいた。前夜の酔いが残っている朱驚男は、不気嫌な気分いっぱいで、ドアをひらいた。
「よォ。おれよォ、回転あげてねえよ。なんでよォ、こうなんだよ。まじめにやってくんねえかな」
「わりィね。よっくみてみっから」
「…たりめえだよ。日曜は箱根にいくんだから……ちゃんとたのむよ」
フルフェイスのヘルメットの奥から、意外に鋭いサービス員の眼が光ったので語尾がちいさくなる。朱鷺男は、こういういい眼(ガン)をとばす、もと暴走族みたいな男は苦手だった。少し離れたところでもうひとり同じツナギを着た若いのがにやにやしていた。
「これ、あんたンだろ?」
サービス員はロードマップをほおってよこす。ギャスタンの脇にはさんで、忘れていたものだ。神奈川全域用の、いちまいものだった。もえこを腰につかまらせて、早春の箱根路をふっとばそうと考えていたのだから。
ニューのバイクには、女はもえこしか乗せていなかった。もえこはバイク狂で、自分でも50CCの変ちくりんなヤツにまたがる。しかし、女子高2年の彼女は通学時のバイク使用を禁止されていた。朱鷺男も仕事があるので、しょっちゅうは寄れなかったが、たまにバイクで下校時の女子校正門へ乗りつけたりすると、もえこのよろこぴようといったらない。クラスメートへこれみよがしに、朱鷺男の細い胴を両腕でしめる。なにかの事情で約束していたツーリングがパアにでもなろうものなら一週間でもむくれた。
赤ペンで箱根へのコースをなぞったロードマップを手に、いかつい肩のサーピス員を見送る。彼は、ギアをニュートラルにした朱鷺男のバイクに乗り、相棒へ合図をした。相棒の男が乗ったバイクから布ベルトが伸びて、朱鷺男のバイクにつながれている。
「お客さん」
フルフェイスのヘルメットがくるっとこちらをむく。
「今日中になおしときますよ」
うるせえ、この次からほかのメーカーのを買う、と朱鷺男はこころのなかでいう。彼らはそろそろと通りへでていった。サービスエ場まで1000メートルもない。通りをぬければ目の前が環状7号線だ。
どんより曇った空から、灰いろのちいさなものが降ってくる。3月の雪だ。朱鷺男は小便がしたくなった。トレーナーのふところに手をいれて、腹から陰毛のあたりを掻きかさ階段をあがった。郵使受から新聞をひっぱりだす。朱鷺男は、新聞はスポーツ新聞しか読まない。
「…ったく、客をおどかしやがンだから…」
部屋にはいると、奥の六畳の間の窓際に置いたベットに横座りして、マツミがコーヒーを飲んでいる。ガスストーヴをがんがん焚いているので部屋のなかはむっとするほどあたたかい。マツミは裸の身体に朱鷺男のコットンシャツをいちまいつけているだけだ。タベ、バイク仲間の井関洋二が別の女をつれてスナックをでたとき、マツミはこれといった表情もせずに、朱鷺男のアパートへ泊めてくれとたのんできたのだった。朱鷺男は酔っぱらっていたこともあったが、あっさり承知して夜なかの2時をまわったころ、もつれるようにして帰ってきたというわけだった。そういえば、井関洋二がなにか大事なことをしゃべっていたような気がする。それがなんだったのか、こころにひっかかっているのに思い出せない。 まいいか、トイレにはいり、どぼどぼと小便を放つ。
「江夏、頑張ってっかなァ。メジャーになれっかな−」
トイレからでて、新間をひろげる。ぱらっとチラシがいちまいこぼれた。めずらしいことだ。新聞屋には広告のチラシ類はいっさいいれるな、じゃまになるから、ときびしくいいわたしてある。チラシいれたら新聞とらねえぞ、とまで宣言してあった。拡張員は、変わったやつだというような顔をしていた。
「それ、みせて」
マツミが手を伸ばす。
朱鷺男はスポーツ新間第1面の朱文字を目で追いながら、マツミにチラシをひろってやった。
「準公選は法律違反です、区民のみなさんポイコットしましょう、だって」
「うっせえなァ。ちょっと黙ってろよ」
「なによォ、あんた中野区民でしょ」
「うっせえってっだろォ。テレビみてろよ」
「あんた教育委員の準公選って、知らないの?」
「おっ、江夏、すげッ。2回を無失点でおさえる。さっすがァ、腹はでててもこころはにしきィ」
「ちょっとォ。ふるいわねえ。あんたホントに20歳?」
「うるせえなァ、おめえより3ッも若えよ」
「しッつれいね。まだ21ですからね、アタシは」
「腹に赤ちやんが5、6人分たまってんじゃねえか」
「ふん。あんたのぷんも、ひとりはいってるわよ」
マツミは脂肪のぽてっとついている横ッ腹のあたりに手をあてていった。
「あ、江川、あ−ダメだねえ。オープン戦から2点もとられてんの。さみしい男だねえ。こころがすさぷよ」
「なんか、たべるもんないの?」
マツミはベットからおりた。スピーカーの上にあった食パンを手にとる。
「このパン、いつのやつ?」
「おととい…・いや、先週のか、忘れた」
マツミが台所に立ったので、朱驚男は自分のベットに這いあがる。今日は仕事にいくつもりはない。昼前にいちおう電話だけはしようと考えていた。
「トースターはどこ?」
「勝手に、さ−が−せ−」
しばらくすると、パンの焼ける香ばしいにおいがしてきた。マツミはコーヒー碗の受け皿にティッシュペーパ−を三角に析って敷き、そのうえにバターを厚く塗ったトーストをのっけてきた。朱驚男のカップには、ちゃんとコーヒーが注ぎ足してある。こういう細かいところに気がつくのが歳上の女のいい点だった。もえこだとこうはいかない。それはベットにいっしょにはいったときでも、おなじことがいえた。
「仕事、いかないの?」
マツミがぶっきらぼうに訊く。朱驚男は顔をあげて別のことをいった。
「よく喰えっよなあ。アフリカの子どもたちをみなさいよ。おなじでてる腹でも深刻さがぜんぜんちがうじゃねえの」
マツミはにこにこしながら、
「あんた、政冶オンチじゃなかったの?熱あるのとちがうかな。ゆうことがあんましまともだよ」
軽く受け流して、2枚めのトーストにバターをびっちり塗りつけた。大きく口をひらくと、角のほうからぐぐっと噛みちぎる。パンくずが、紅い唇のまわりにいくつもくっついた。
「あ−いやだ、いやだ」
朱驚男は新聞をひろげて顔にかぷる。マツミはそのようすを横目にみて、ふんと鼻のさきでわらった。
「そういうあんたは、夕べアタシのあそこにクップクした」
平然と、しかしさりげなく、そのセリフは吐かれた。
「な、なりゆきだから、しょうがねえベェ」
ガザガザッと顔から新聞をとって、ベットに起きなおる朱驚男だ。
「それ、どこのことば?」
マツミは眉をひそめる。話をそらすのだ。
「丹沢のふもとで生まれたんだから、しゃあないじゃん」
「気をつけなさい。育ちがわかるわよ」
「か−ッ。なにさまだってかよ、自分は」
実はマツミが、れっきとした中堅どころの不動産会社の社長令嬢だということは朱鷺男も知っているのだ。最初の男がわるかったらしくて、短大を卒業してもまだ遊びっばなし、家出同然に家(うち)をあけている。ちいさいころからずっと、他人にたかられていた、と話したことがある。それでずいぷん人気者になっていたが、ある日、ふと気がついて、たかられるのを拒否した。すると、まわりに人間は誰も残っていなかった、というのだ。男にくっついて遊んでまわっているのは、それまでのうっぷんばらしなのかもしれなかった。
「あんた、投票のはがき、どうしたの」
「あ・…・・?」
「教育委員、準公選の投票はがき」
「…んなもん……ねえよ。すてちまったよ」
「そ」
マツミはそれ以上追及してこなかった。そういえば井関洋二はいっていた。マツミには、時どきみょうにまじめなことで根ホリ葉ホリやられるからかなわない、と。
「それ、とって」
ベットの窓側に、マツミの着ていたものがたたんである。朱驚男は腕を伸ばしていっぺんにつかみ、ほうりだした。
マツミはコットンシャツの前ポタンを手品のように外して、足もとにおとす。色の白い、なで肩の、日本人的な、どこかしらなつかしいような気のしてくる体型だ。胸は張っているし、尻にも量感がある。
「やだ。下の、むこうにおちてない?」
かがみこんで、ブラジャーをつけながらいう。マツミのところからだと、衣類用のカラーポックスにさえぎられて反対側はみえない。朱驚男が壁とベットの隙間をのぞいたら、マツミのたくましい骨盤をおおうにはこころもとなくみえるきゃしゃなパンティが、ヘんに生なましくひろがっておちていた。
「だからッ。花粉症と風邪と両方でたいへんだってゆってるでしょう」
(でてこい。わかってんだ、おめのこた。きのうの配達分が、まだいっぺえ残ってっじゃねえか。花粉症ぐらいで休まれてたまっか)
「もっと従業員の健康のことも考えてくださいよ」
(知恵のあるふりせんでもいい。でてこッ。若いうちは働いとりゃあ風邪なんか自然になおる。わかっか)
「無理いわないでくださいよォ」
(おめ、店が忙しいときズルしようってか。美平さんにアパート、寄ってもらうぞ。どうせ女と寝ておるくせに。一人前のことほざきやがって。いいか、仕事にやリズムがあるんだ。這ってでもこいッ)
電話が切れた。3分半の演技も空しい。米屋の黄いろい電話は、もうツーツーいうだけだ。社長は、巾が15ミリは確実にあるあの眉毛をぴくぴくさせているにちがいなかった。それにしても、ちかごろの若ものにああいういいぐさをして、このさきやっていけると恩っているところがふつうではない。もし、あの社長が自分にとって伯父さんでなく、もえこの父親でもなかったなら、とうのむかしにどっかへ逃げだしていただろう。高校中退後の、この2年間の無粋な長さをあの男はたぷん知らないはずだ。10円玉がこつ−んと返却口にもどる音を朱鷺男はしらじらした気分で聴いた。臍のあたりに、風邪の病原菌がぺとぺとくっついてくるようなこころもちだ。が、とにかく社長は無視すればいい。金の亡者だ。娘をいただかれてるなんて夢にも恩ってないだろう。デリケートなところは胡麻粒ほどもない人間だから。
しかし、美平(みひら)のじいさんがくるとなると話は別だ。朱驚男はあの人物がどうしても好きになれない。なんだか簿気味わるいのだ。4、6時中わらっているような口もとへもってきて全体にゆるんだようなたたずまいだ。昨年の春と秋、それぞれ半日、アパートのドアの前に立たれて閉口した。いずれも社長の命令でしたことなのだ。秋のときは、泊まっていたのが高校時代のワルで、夕方にはどうしてもという用事があったから、とうとうじいさんに根負けした。あれをくりかえさせられるとなると参ってしまう。一見して好々爺だが、自分からはあまりしゃべらず、他人にいわれたことだけをもくもくとやるようなところなど、ちょっと理解できない。顔をあわせて2年たとうというのに、どうにもなじめなかった。
美平のじいさんは都営住宅にひとりで住んでいる。場所は、環7の丸山陸橋を越えてしばらく板橋方向へ下り、左析して7、800メートルはいったところ。練馬区だ。つれあいが数年前に死んで、平屋の老旧住宅にひとり残された。子どもの話は聞いたことがない。
老人の家の庭は盆栽で埋っている。通勤の途中、なにげなく目をやると、ちょうどいまの時期、梅の鉢がことにみごとだ。丹精しているのがひと目でわかる。仕事は、朱驚男の勤めとおなじ園芸店で、主として植物の世話をしているのだ。趣味も本職もいっしょだった。好都合なことに、仕事場は住まいから目と鼻のさきにある。ここら一帯は、まだまだ武蔵野のおもかげが残っていて、びっくりするほど広い畑や、大きな棒(けやき)を擁する農家が点在していたりした。
朱驚男のアパートは、西武新宿線の野方駅にちかい。ここは中野区だ。園芸店から美平のじいさんが、ナショナル自転車という黒くて重たい骨董品に乗ってきっこんぱったんやってくるとなると、ものの12、3分で着いてしまう。
あはあ…よんでるよ……
朱驚男の顔をみて、歯のない口をあけ、そういうことをいうはずだった。あのじじいにこられちゃあたまんねえや──アパートの階段をだだっと駆けあがった。
マツミは裸のまま、蒲団をかぷってとろとろ眠っている。なんだかんだといってみても結局、女の密度そのものにはくりかえし結合意欲をそそられてしまう。さっきも、ついズポンをおろしてしまった。夕べだってかなり頑張ったというのに、なにが不足だったか、こいつばかりは最限なし。
マツミの肩をつかんでゆりおこす。
いちんちに18時間眠るというコアラのような目をして朱驚男をみる。やばいじいさんがくるので外にでよう、と話した。すると、おもしろがってベットから離れようとしない。ぐずぐずしていると昼になる。そうなれば社長は美平のじいさんに出動を命じるだろう。実力で女をベットからひきはがそうとした。だが相手はこちらの弱点をよく知っている。あっちこっち、こちょこちょくすぐられるとすぐおかしな気分になってしまう。すると、なにもかもどうでもよくなった。考えてみなくとも、たまのズル体みくらいは大目にみてもらっていいはずなのだ。
梢園芸は、いまの社長がちょうど10年前からはじめた店で、それまではピニールハウスに野菜をつくったりしていたという。思いきって畑を宅地に賃貸しし、残った土地に温室を建てた。園芸備品を売る店も併設し、ちかごろは観葉植物のレンタルにまで手を伸ばしている。そのうえ温室の一角を喫茶店風に改造して、そこで客にコーヒーまで飲ませだした。従業員はたまったものではない。毎日、うんざりするくらい忙しいのだ。どっかのテレビ局が、温室のある喫茶店といって中継したときも、社長以外の人間はしらっとした表情だった。あんまり仕事がきついので、社長の同族ではない人間を雇ってもすぐやめてしまう。あたりまえだ。労働基準法みたいなものが適用されるわけではなし、給料も知れたもの。神奈川とか埼玉の農家や、園芸組合に仕入れにいくのでも、いくら時間がかかったところで割増しはおろか出張手当もなかった。従業員はパートふくめて8人で、唯一、不平をいわないのはこれが社長と血縁関係のない美平のじいさんくらいのものだった。
その美平のじいさんが、アパートのドアを弱よわしくノックしたのは午後も2時近かった。音で美平のじいさんだということがわかる。ドアの外はずいぷんさむいだろうに、この老体が粘り強くほとほととドアをノックしつづけるのだ。
朱驚男はマツミの身体をぴったり抱いている。この体勢になると、ちっとやそっとでは起きあがれるものではない。女の忍びわらいが部屋の壁を這いまわる。壁には、癌で死んだマックィーンがル・マンのときのレーサー姿で遠い目をしている。女の秘かな声と、あたたかくてやわらかな身体のうちにいると、神経が休まった。
すこし、うとうとしたようだった。間き覚えのある声が外から届く。ト・キ・オッ。トキオガソラヲトブッ……あれは、もえこの声だ。鉄骨でつくった階段だから、はねるような足どりがドアのこちらにもよく聞こえてくる。
(おじいちゃんッ。なにしてんの。アイツ、まだ寝てんのッ)
きんきらきんの声が、そこいら中に響き渡っているだろう。なんでまた、いまごろアパートへ訪ねてきたのか。朱驚男はすっかりあわててしまった。それと同時に昨夜、井関洋二に聞かされた話を思い出していた。もえこのはいっているロックバンドを狙っている連中がいる、というまじめな話だった。関東○○会という組織がらみのことだという。井関洋二は冗談の好きな男だがうそはつかない。それが事実ならはやいとこ手を打たなければならない。それなのにいまごろ思い出している。だからといっていま、でていくわけにもいかない。
(おじいちやん。そういえばバイクないよ。アイツ、どっかいっちゃってるよ。帰ろう)
しめた、と思った。このまま、あのクソじじいをつれて帰ってくれればありがたい。マツミは身体をふるわせて、わらいを押し殺している。
ガラッ!と台所のガラス戸をひきあける音がした。心臓がどきどき鳴りだす。施錠していなかったのだ。うかつだった。格子がはまっているから、外から中へはいることはできないけれど、玄関は丸みえだ。せまいコンクリートの三和土に、マツミのハイヒールが朱鷺男のス二−カーとならんでいる。しまった。未鷺男はマツミの顔をみた。
10秒、15秒……音がしない。突然、ガラス戸を激しくしめる音がした。カン、カンと階段を駆けおりる音がつづく。それがすむと今度はそれこそほんとうに静かになってしまった。ワンブロックむこうを走る西武線の電車の音が耳の奥でするくらいだ。窓のカーテンをひくと、まだ夕方には早いのに空は暗くこごえてみえる。ふたりとも、ひどく腹が減っていることにあらためて気づいた。
衣類を身につけ、ストーヴを消し、マツミを促す。
「このへん、おいしい店、ある?」
コートを着ながらマツミは、これから喰うものについて自分の夢を語るようだった。朱鷺男は、なじみの中華料理屋がだす650円の定食のことを考えていた。とにかく、人間らしい喰いものを腹にいれなけれはならない。マツミの弾んだ声音に少しょう辞易しながら朱驚男がドアをひらくと、表にはまだ美平のじいさんがぼうっと立っていた。
カプセル建築法式で魔法のように出現した家にひとがもう住みついている。せまい庭は、まだ黒ぐろとした土ばかりだ。朱驚男がこの家に届けたのは、もう黄いろい花の咲いている三種(みつまた)、さんしゅゆ、それとこわばった蕾の紫木蓮。地面というのもおこがましいような、わずかな泥の平面に、あのひとたちは花木を植えるのだ。そして、せめても季のうつろいを知ろうというのだろう。サーピス品の油かすの袋をトラックからおろす。
おとなしそうなサラリーマンふうの男と、若い奥さんと、えらいスピードで動きまわる女の子のトリオが手ぐすねひいて待っている。このさき、たいして使いみちなどなさそうなスコップだの剪定鋏だの新調して。
住宅街の入り組んだ道路を、標識に従って遠まわりをくりかえしながら軽トラックを走らせる。いまのような仕事も客も、なんだか虫酸が走る。コンパクトにまとまった感じがいやなのだった。
店に帰ると、表のフェンスのところで社長が美平のじいさんをつかまえて文句をいっていた。
「美平さん、そんなもんここに貼られちゃ困るといっておいただろう」
じいさんがなにかいった。聞こえないくらいのちいさな声だ。
「だめだ。はじっこだろうがどこだろうがだめなもんはだめだ」
社長は自分の親のような人間にも容赦しないくちぶりだ。
美平のじいさんはなにかのポスターをもって塩垂れている。
朱鷺男が車を車庫にいれてキィーを返しにいくと、社長が晩めしを喰っていけという。5時半で、あたりは暗い。今日も丸いちにち曇っていた。午前中は氷雨だった。身体は冷えているし、家庭的な料理にもありつきたいが、断わった。ヘルメットをかぷり、バイクにとりつく朱鴛男に、社長は釘をさすようにいう。
「休みたきゃ、せめて前の日にいえ。死にもの狂いで働かねえやつが、そんなもん乗りまわしてカッコだけつけやがって。おれは妹からたのまれて、おめのようなできそこないをあずかってんだ。調子づくな」
朱鷺男は返事もせずにバイクをスタートさせた。きのういっぱいサービス工場でなでまわされたせいかバイクの調子はいい。環七の車の流れへひと息にまぎれこんだ。
社長のいう〃妹〃というのはもちろん朱鷺男の母親のことだ。高校中退ではろくな就職先もない、と伯父の園芸店に働き口を求めた。丹沢の麓から、東京にでてきて2年。道路に充満する排気ガスを吸って生きている。たしかに自分はできそこないかもしれない。金積んではいった私立高さえ卒業できなかったのだから。だが、それだからといって、なぜ馬鹿みたいに働かなければいけないのか。あくせく働いてばかりいると、それ以外に能のないような人間になってしまいそうだ。社長がいい例だ。あの男は働くことが趣味で、金を貯めることが生きがいなのだ。なるほど、うまく隠しているが若い女がいることはいる。たまたま目撃したに過ぎないが、けちなマンションに住まわせている。金なぞ腐るほどあるのだから派手にやればいいのに、あれでは愛想つかされない程度にしか金は渡していないにちがいない。なにごとにつけ仕事優先の男だ。
朱鷺男がバイクをきしらせて走りこんだのは、区の青年会館だ。もえこがクラスメートとつくっているロックバンドの、練習の日だった。地下に防音壁で囲った室が設けてある。工事が不充分なのか、だいぷ音がもれていた。もえこが、せいいっぱい甘ったるい声をだしてタイムマシンニオネガイ、と歌っている。むかしの歌だ。二重ドアを押してなかをのぞくと、もえこが歌いやめた。
ポーカルのもえこにドラム、ベース、キーボード、ギタ−の4人がついている。なかのふたりは女子高の制服のままだ。部屋のすみに男が3人いた。ふたりは牡ライオンのように髪を逆立て、金いろに染めている。こいつらはバンドのアドバイザーらしく以前にも何回かみたことがある。残る見なれないひとりは濃いサングラスをかけて、ヒゲを鼻の下にたくわえているちょっと年輩の男だ。いかにもその筋という感じがした。そいつが顎をしゃくると、ライオン髪のひとりが朱驚男のほうへゆったり歩み寄ってきた。するともえこがそばへきて腕をひく。
「あたし、話すから。あのこたち教えてて」
朱驚男の目はみずに、さっさとドアの外へでた。男たちはバンドのほうへいく。朱驚男はなにから話そうかと迷ったが、ともかく外へでてもえこの横に立った。
「むかえにきたんだ。練習がおわったら、ちょっとつきあえよ。話あっから」
「帰れよ」
さっきまでのキャンディー・ポイスとは別人のような、冷たい声だ。もえこは床をにらんでいる。
「帰れっつってんだよッ一バーロッ。…ざけやがって」
「でけえ声だすなよ。話ぐらいいいじゃねえかよ」
「てめえと話すことなんかねえよ」
「誤解すんなよ。話しゃあわかっから」
そう口にはしたが自信はもちろんない。
「みっともねえ、いいわけなんか聞いてらんねえよ。帰れ、ポロアパートに」
おしまいのひとことが朱鷺男にはかちんときた。ちいさなアパートになにも好きこのんで住んでいるわけはない。それも給料が安いからだった。手取り14万に満たない自分にあれ以上のアパートがあるだろうか。バイクを買ってからは飲みにいってもひとにたかっているような状態だ。いや、そうではない。それだけではない。もえこのことばの背後には裕福な家に生まれ育った人間の優越感がこめられている。そういういくつかの思いが、いっしゅんのうちに煮えて吹きだした。
階段を駆けあがって、植えこみのそばにおいていたバイクにとび乗る。頬を張ったが、あと味がわるい。さっきまで胸がうずくほど愛しかった女だった。17歳の記念の日に、朱驚男と初体験する約束を、きょ年の冬に果していらい、将来のことなんかもぼつぼつ話すようになっていたのに。
広い道路にでると、スロットルをいっぱいにひらいた。もえこの、あのひとことがにくかった。同時に、自分がどうにもならないほどいやな人間に恩えた。はっと前方の信号に気づく。赤だ。バイクを横倒しぎみにしながら急ブレーキをかける。停止ラインを3メートルも越えてやっととまった。信号待ちしていたタクシーのなかから、バカヤロウッ!と酔っぱらった客の怒鳴り声がした。
環状7号線は昼夜をわかたず車の洪水だ。信号が変わると、まるで競争でもするようにまわり中が捻りだす。まっさきに、どの車よりも速く、朱驚男はマシーンと一体になってとぴだすのだ。ト・キ・オ、トキオガソラヲトブッ、か……ふるい歌うたいやがって。ちきしょうめ。おれは、こんなことでしか、いちばんになれねえのかな……。
冷たい空気が朱驚男のまわりを、簿板がはねるような圧風になってとりまいていた。
休みの目も雨だった。朝から外が雨音でうるさく、昼までベットのなかにいた。午後になるとすこし日が射してきたので、環7沿いにあるファミリーレストランのランチを喰いにでた。圧倒的なボリュームのハーレーが、10台もレストランの駐車場にとめてある。朱驚男は愛車を駐車場の端っこにとめた。とてもならべておく気にはなれなかったのだ。ハーレーはいずれも排気量1000CCを越えるものばかりで、白銀いろに輝いている。
レストランにはいると、環7の車の流れがみえる窓際に、渋い中年ライダー族が談笑していた。着ているものも朱驚男のような安物の皮ジャンではなくて、ヨーロッパの航空兵でも着そうな格調を感じさせる代物だ。禿顕の男はボンバーを無雑作に両肩にひっかけて、でかいパイプをくゆらせている。由緒正しそうなゴーグルをもて遊んでいる男はよく日に焼けていて、鼻髭が決まっている。どの男をみても、ひとくせありそうで、しかもどんな境遇にも負けないような態度にみえる。ひき比べて、自分のちいささに身が縮む。いつかは、みていろ、おれだって。くそ、ハーレーなんか、芋が乗るんだ、うらやましいことなんかあるか……ランチの味がしない。
食後のコーヒーも飲まず、レストランをでた。あの雰囲気のなかにいたくなかった。エンジンをかけて、なに気なく顔をあげたら、ちょうど窓のむこうで男たちがどっとわらったところだった。朱驚男は自分がわらわれたような気がして身内がかっとなった。ちんけなワッパころがしやがってと、そうわらわれたような気がしたのだ。しばらく走ってやっと気をとりなおす。いつのまにか園芸店の近くにきていた。
ダークグリーンのトランザムがフェンスの横にのさばっている。自い鷲がフロントに幾何的な羽根をひろげていた。もえこのクラスメート、バンドのメンバーがふたりと、先日、青年館にいた若い男のうちのひとりがアスファルトにしゃがんでいる。園芸店の前庭はパンジーやフリージアなどの春の花でいっぱいだ。そこで、もえこと社長がいい争っている。
「もお、いやだっつってっだろッ。バカみてえに店番なんかしてらんねえよ」
「ちゃんと店手伝うというから大学までいかせてやる約束だぞ。働かねえなら高校もやめちまえ」
「自分の娘だろ。自分の娘が高校もでてなくて恥ずかしくねえのかよ」
「かんちがいすンな。将来恥かくのはおまえだ。どうせおれはさきに死ぬ。はやくエプロンとってこッ」
「やだよッ。世間の親をみてみなよッ。どこに子ども働かせてンよおッ」
「世間の親がどうした?あん、貧乏ったればっかりじゃねえかッ。おれがおまえに不自由な思いさしたことあるか、月5万のこづかいに、ステレオだ、アンプだ、ふざけんな!さっさと店の掃除しろッ。コーヒー豆、挽いとけッ」
「やだよッ。いらんねえよ、こんな家(うち)」
「家がいやならでていけ。そのかわり、どこで死んでも葬式代はださねえぞッ。ロックバンドだと?そんなもんでメシが喰えりゃ若いやつァみんなやっとらァ。店、あけて、湯わかせッ」
「……やだ…よォ」
もえこの鳴咽がフェンスを越えてくる。しゃがんでいた若い男と女の子たちがへらへらわらっている。
「うるせえよッ!」
朱驚男が声をだすと、みんな黙ってしまった。バイクのスタンドをおろして、助走をつけ、フェンスをとぴこえる。たくさんの花の鉢が、ところせましとならんでいる。いちおうは休みの日なのに園内には近在からの客がけっこうつめかけているのだ。それで親族でこれに対応しなければならなくなる。とんでもない迷惑な客ばかりだ。それなのに、みんなこの親子げんかをみてみぬふりしている。
もえこ、箱根にいくぞ、とカッコよくいうつもりだった。ところがそうはいかなかった。横あいからもえこの母親がタオルとエプロンをもってとびだしてきた。この、日頃めだたない女が、さっと娘にとりついて、あっというまに第三者の近よりがたいバリヤーをはりめぐらしてしまう。
とうさんはきついこというけど、ぜんぷおまえのことを思っていってるのという、例のやり口だ。これにもえこがあっさりひっかかってしまうのだ。母親とふたりで喫茶店のほうへいきかかる。だが、そのまえに朱驚男は社長と目が合ってしまった。社長はちょっと驚いたような表情をみせたが、すぐに今度はひとをさげすんだような顔になった。それで朱驚男は頭に血が昇ってしまった。獣声というと、獣に失礼になるような、そんなわけのわからない声をだして社長にとびついていった。とたんに目の前が真っ暗になった。
アイツハ、コロスンダヨーと、どこか遠くで声がしている。はっと蒲団をはねのけた。そこは重く粘った空間だ。思わず背筋がぞっとする。ちぢこまりながら、ちょっとずつ目をあけていった。その薄目をあける速度に応じて夜が明けたような気がする。
たくさんの鳥が集まったような声がしていた。耳をそばだてると、10人くらいの婆さんたちの声がいちどきに鼓膜を襲う。あいまに美平のじいさんの楽しそうな声がしていた。
起きあがって小便をしにいく。平屋の都営住宅だが、きちんと掃除がしてあった。便所もきれいなものだ。年寄りが集まっている部屋の床の間には天照大御神の掛け軸がかけてある。明治天皇と皇后の写真もきちんと掲げてある。年寄りたちはみんな、ちいさなカラー刷りのパンフレットをひらいていた。朱鷺男の顔をみて、ひとりがパンフレットの表紙をみせてくれたが、そこには、おなじみのチョビ髭をたくわえた人物が蒼い空をバックにしていずれ知らぬ空間をみつめていた。
頭が痛むが、徐々に事態が呑みこめてくる。ヘマをやって、美平のじいさんの居宅にかつぎこまれたようだ。社長にとびかかったものの、てんで歯がたたなかったらしい。
「やっぱり○○先生じゃないといけませんよ」
「ここはいちばん負けられませんからね。国を滅ぼすんですからね、あいつらは」
「みなさんそこをよく訴えて、よろしくお願いしますよ」
「あとひと押しですからね」
婆さんたちはにぎやかにお互いに声をかけあって外へでていく。
煙草が無性に吸いたくて、ほうりだしてある皮ジャンをさぐった。火を点けて、大きく吸いこむと、やっと落着ける。蒲団の敷いてある六畳間の壁に目をやった。でっかい世界地図だ。美平のじいさんは例のパンフレットをながめてにこにこしている。
「じいちやん、もてるなあ」
ばあちゃんたちがいっぱいきてるじゃねえか、いつもこんなふうかい、と朱驚男はからかってみる。照れると思いきや、美平のじいさんはまんざらでもないような顔をして、
「選挙、ちかいからね」
といった。朱驚男にはなんのことかわからなかった。
床の間には、みごとなミニ盆栽がおいてある。生かさず殺さず150年といったようなキチガイじみた生きている植物のオブジェだ。煙草を盆栽の下の皿にもみ消して、たちあがった。そのひょうしに壁の世界地図をみなおして、ある奇妙な感覚にとらわれ、思わずまたしゃがみこんでいた。世界地図の色わけがおかしいのだった。なんだかへんだなあ、と思ったら、世界の陸地の半分くらいまでが朱い。あかるい赤のマジックで塗りつぷしてあった。
「あの、ね……」
朱鷺男がとまどっていると、美平のじいさんがさも大事なことを話すといったようなそぶりで近寄ってきた。
「ほんとうは、ね。みんなね」
日本の領土だったんだよ、と老人はいった。朱鷺男は老人がなにをしゃべっているのか、さっぱりわからなかった。
「自分は知ってるけどね。日本は負けちゃったから。でもね、ほんとうは、ここも、ここも、みんな日本の領土だったんだよ」
なにをほざくんだろう、このじじいは。世界の半分が日本の領土だったなんて、このじいさん、頭がおかしいんじゃないだろうか。
「みんな、知らないけどね。自分、ちゃんと知ってるんだよ。負けたから、とられちゃったけどね。ほんとはね。みんな、日本の領土なんだよ」
そういって、にっこりわらった。
朱驚男はぞっとした。立ちあがって皮ジャンを着る。すこし頭がふらふらするが、身体のどこといって痛くはなかった。
「じいちやん、世話ンなったな」
玄関へ歩きかかると、美平のじいさんが、ちょっと、とひきとめる。あげたいものがある、というのだ。なんだかしらないが、ほしくない。あがりかまちに腰かけてスニーカーの紐を結ぷ朱驚男のかたわらに、美平老人は平たい木箱をもってきた。蓋をとると、色のあせた布きれがきちんと畳んではいっている。目のまえで大きくひろげてみせた。
それはでっかい旭日旗だった。4、50年もむかしのものだろう。これ、あんたにあげるよ、という。ずいぷんとっぴな話だと思った。この2年、そう親しくしてきたわけでもないのに、いきなりこんな好意を示されるというのがわからなかった。そのうえ、もらったところで使いようもないような品物だ。せいぜい壁に画鋲でとめておくぐらいのことだろう。それも変わってていいか。
「これ、じいちゃん兵隊のときのやつかい」
つやのいい顔を、骨ばった手でぷるっとなでる。にんまりうなずいている。
「自分、海軍だったからね。でも、それは戦争が終わってから買ったんだよ。燃やしてたのを罐詰ひとつで、こんなにね」
両手を上下に40センチほどひらいてみせた。
「それで、どうしたわけ?」
「袋をつくって、そのなかで寝たよ」
「へ−頭いいじゃん」
「負けなかったら、ね。よかったけどね。負けたから」
「じいちやんは生きてっから文句ねえべよ」
「いいことなかったね。むかしはよかったよ。人情があったから」
老人は急に暗い表情になった。心底そう思っているらしかった。朱驚男はようやく気がついた。他人にいわれることに唯唯諾諾として従っているこの老人も、こころのうちには大きな不満をもっているということを。
「あのね…・」
玄関のドアに手をかけた朱驚男に、美平のじいさんは細い声で呼びかけた。
「あんなやつは、殺したんだよ。むかしは」
また、おかしなこといってらァと思ったが“あんなやつ”とは社長のことだと気づくと朱驚男はぷりかえって、美平のじいさんの顔をまじまじとみた。
「むかしはね、あんなやつは殺したんだよ。おかみがしっかりしていたから、コクジハンとかね、あんなやつもみんな殺したんだ」
そういえばこないだなにかのポスターを園芸店のフェンスに貼ろうとして社長に怒鳴られていたが、あんなことでそこまでいうか、という気がする。
「じいちゃんよ」
朱驚男は旭日旗の箱を手にかざして訊ねた。
「なんでおれなんかにくれンだよ、これ?」
美平のじいさんは顔をあげて今度はみるみる明るい顔になった。しんそこゆかいそうな表情だ。そしてこたえた。
「それは、若い衆(し)がもっとくもんだからね」
道路のむかい側に、『梢園芸店』の看板がある。フェンスが温室を囲んでずっとつづいている。朱鷺男のバイクはフェンスにそうようにしてとめてあった。ヘルメットは後部にくくりつけてある。細かい雨が降っていて、ヘルメットのなかにはひと晩ぷんの水が溜っていた。
「今朝ははやいじゃないか」
社長が道路のまんなかにでてきた。
「朝メシ喰え」
爪楊枝を口のはしにくわえて、作業ズポンに両手をつっこんでいる。白髪一本ない、みっしり生えた髪に雨滴が極小の玉をいくつもつくっていた。朱驚男は返事をせずにバイクへとりつこうとしたが、皮ジャンの胸ぐらをひっつかまれてひきずられた。もの凄い力なので、せいいっぱい低抗してもずるずるもっていかれる。
「メシなんか喰いたかねえよッ」
「なら喰わんどけ。今日は忙しいぞ。百年経っとる松2本掘って、葉山いくんだぞ。きついぞ」
「仕事なんかしたかねえってっだろッ」
「ばかやろう。きのうの根性がありゃあなんだってできら。いいからこい」
園芸備品を売る店のとなりに、社長の家がある。10以上も室のある2階建てだ。朱鷺男は現在のアパートに移る前に、しばらくここの2階にいた。
玄関をどたどたあがって、ダイニングキッチンにはいる。もえこが、こんがり焼けたトーストにマーガリンを薄くのばしていた。男ふたりがはいってきたのでびっくりしている。よくみると両方の目が真ッ赤だった。ひと晩、泣いていたのかもしれない。
「おい、こいつにメシ喰わせろ」
朱驚男を椅子に座らせて、社長がいった。奥方は目鏡の奥の目をきょろきょろさせていたが、トキオチャン、パンにする、ゴハンがいい?と訊いた。とたんに社長が吠えた。
「メシを喰わせろといったろうが!」
それで井飯がでた。味噌汁もある。もえこがなにかいいたそうな顔をしたが、はやく学校にいけ、と社長に追っぱらわれてしまった。
朝食が済んで、すぐに仕事の準備だ。小雨はやんでいない。土がゆるくなっているから着ているものは汚れるし、道具はぬかって掘る仕事はたいへんなはずだった。
「おはようさまです」
美平のじいさんが例によって地下足袋姿であらわれる。なんの表情もない。
「美平さん。昼に区長の紹介ってやつがくるから、五葉松の棚をみせてやってくれ。値切りやがったら帰ってもらっていい」
老人は深ぷかとおじぎをする。液肥の調合に水道ばたへむかうその後ろ姿には、なんの感情もあらわれていない。
午前中いっぱい、小糠雨に濡れて老松2本を掘りだしながら、朱驚男は美平老人の希代な地図と、貼りついたような微笑を何度も思い返した。仕事は、社長とほかにふたりきて大の男4人がかりだったが、冷たい雨にもかかわらず、カッパのなかはサウナにはいったときのように汗で蒸れた。この土地にも、建築基準すれすれの、圧縮したようなマンションが建つようだ。掘りだした松は、樹齢を考えれば意外なほど小ぷりで、地を這わすように形づくってあったから、たいして苦労もせずにトラック2台へ積みこめた。
第3京浜から南横浜バイパスを通って、葉山の、とある豪壮な邸宅ヘ。掘るのはやすかったが、定植はたいへんだった。いったん植えこんだのに、その家の主が何の気まぐれか位置がわるいといいだしたのだ。客の気の済むようにと次の場所を4、50センチも掘りさげたらおおむかしの海岸にでもあったような牡獲殻つきの大岩だった。
帰りの道はフロントガラスに斑(はだれ)がぷつかっては消え、流れた。環7にはいって信号待ちしていると、前方を横切るナナハンが目にはいった。井関洋二自慢のオロロン号だ。長崎出身の井関洋二は、オロロン、オロロン、オロロンばい、と歌ってバイクに乗るのだった。風防が特注なので、すぐに見分けがつく。それより間題なのは後部席に乗っていた女だ。井関洋二の腰につかまっていたのは、あれは、もえこではなかったのか。
ピンクのキルティングも、赤に白ラインのヘルメットもほんのいっしゅんではあったが、みまちがうわけがなかった。朱驚男はトラックのハンドルを大きく切って横道へ侵入した。いっせいにクラクションが鳴る。居眠りをしていた助手席のおっさんが、ライトの交錯する外のようすに驚いている。幹線道路からそれると目標を失いがちだが、この2年、練馬近辺はゴミ集収車よりこまめにまわっている。ちくしょう、あの野郎、「火の国からきた女たらし」だとッ。もえこにまで手ェだしやがって。だが、トラックとナナハンでは入り組んだ街路上で勝負にはならない。朱驚男のあせりをあざわらうように、子守唄のひとふしを名にもつバイクは、どこかへ消えてしまっていた。
もえこの母親が騒いでいた。まだ10時にはなっていない。スポンジは室温で乾いていた。水分のないのをたしかめて、ヘルメットをつける。母親というのは、どうしてああなのか、と思ってしまう。おろおろしている。社長が名前を呼ぷ。目をむけると、ウィスキーを瓶ごと呑んでいる40男の冷たく怒ったような顔があった。
「おめ、もえこのゆくさき知ってっか?」
朱驚男は首をふった。
「おめ、もえこと寝たろ?」
ぎくっとしたが、嘘はつけなかった。うなずく。顔の横15センチを、ホワイトホースの丸瓶がうなりをあげて飛んでいった。ドアがあいていたので、夜の闇のむこうで瓶の割れる音がした。しばらく睨みあいがつづいた。
「あんた、きちがいだよ」
「おめ、は、できそこないだ」
「そうだよ。あんたはきちがいだ」
「きちがいだから、やっていけるだろうが」
「おれ、もうしらねえや」
「よくみろ。きちがいとできそこないで仲よくやってっだろうが」
「関係ねえよ。おれ、あいつ探しにいくからな」
「いってこい。つれて帰ってこい」
「うるせえよッ。あんた命令なんかすんなよ。だれだって気持ちよくなんか聞いてねえぜ」
「一人前のこと、いうな。なんだって、やってやってるだろうが」
「うるせいってっだろッ。おれはおれでやるよ」
バイクをスタートさせようとして、ふと例の木箱に気がついた。バイクのそばにおちている。なかみをとりだした。街灯のなかに、退色した朱が煮こごりのようなつやを放つ。朱鷺男は旭日旗を背なかにはおった。降りしきる冬のなごりの、淡雪よけだ。マントをなびかせて風を切っていく。あの、ふるい歌が、また耳によみがえりそうだった。
夜のなかをひた走ると、都市の隅ずみに雑多な声があることを知らされる。あるグループが教えてくれたことによると、もえこたちのバンドは悪質な業者の手にかかっているらしい。井関洋二のもたらした情報はたしかだったのだ。マリファナや覚醒剤の果てに、底なしの転落が用意されている。朱鷺男はあらためて自分のうかつさに気付き、頭がおかしくなりそうだった。
明け方ちかく、なじみのスナックまできてみると、オロロン号が雨露をあびている。スナックのドアを蹴破るようにしてはいったところには、酔っぱらった井関洋二と、めっぽうアルコールに強いマツミが空のボトルをはさんでご満悦だった。井関洋二が朱鷺男の顔をみていった。
「なんばしよったと。遅かあ。空ば飛んでこんかあッ」
寝ていないのと気がたっているので、井関洋二の周囲50センチぐらいの首をぎゅうぎゅう締めてしまった。朱鴛男をとめたのはマツミだ。
「彼女ならだいじょうぶ。洋ちゃんがうまく助けたんだから。あんた、興奮するとけっこういい男になるね。ばかがなおると、なおいいのにね」
もえこは、このスナックの2階で寝ているという。なじみ客の連れ、というのでマスターが許可してくれたとか。井関洋二に謝って事情を訊ねた。
もえこたちのバンドにつきまとっていた男のうちのひとりは、なにもわからない少女たちをだましてビデオに撮ったり、その筋に売ったりする常習犯だったのだ。井関洋二が両性の合意に基づいて話を聞いた女性たちに、そいつの被害者が何人かいたというわけだった。
「でも、あんた、それいくらなんでもアナクロじゃない?」
「グロばい。グロ。グロテスク」
いわれて自分のかっこうをぷりかえる。旭日旗をはためかせた、まぬけなスーパーマンだった。
「トキオッ」
階段の下に、もえこが目に涙をいっぱいためていた。
泣きじゃくりながら身体をあずけてくる。ごめんね、ごめんね、といっている。マツミがばちんとウィンクしてみせた。たぷん、うまくだまくらかしてくれたのだろう。
朱鷺男はもえこを胸に抱きながら、あいているほうの手の親指とひとさし指で丸印をつくった。もちろん舌をだしていたが。
もえこは家に帰りたくない、といった。父も母も、好きだがいっしょにいたくない、と。朱鷺男とずっといっしょにいたい、というのだ。スナックの外がすっかり明るくなっている。マツミがいった。
「逃げちやいなさいよ」
みんなびっくりしてしまった。マツミは平然とつづけた。
「ぜんぷほっぼりだしてさ。逃げちゃえば。バイクもあるし。ほら、天気いいよ、今日は。すてておしいもの、なんかある?」
そういわれて考えたが、六畳と四畳半のアパートに、すてておしいものが何ひとつないことに朱鴛男はいまさら気づかされた。同時に、皮ジャンの内ポケットにロードマップをつっこんであったのに気づいた。箱根への赤ラインがひいてある。みるとなにか狂暴な血がたぎってきた。
「寝てなくて、だいじょうぶ?」
もえこが訊いた。キャンディーの味の声だった。
「しっかりつかまってろ」
朱鷺男はこたえて、朝の空気をふるわせるエンジン音をあたりいっぱいに送りだした。もう、通勤客たちが駅へと道をたどっている。
教育委員の準公選に参加しましょう──
西武線の駅のほうで、宣伝力−が呼びかけていた。
わたしたちの手で、選びましょう──
「これ、どうすんの?」
マツミがわらっている。旭日旗だ。
「記念にとっとけよ」
「あたしがふられた記念?」
しばらく沈黙があった。やがて、なんとなく4人はぎこちなくわらって、そのわらいも消えないうちに、猛スピードでバイクのふたりは走り去っていた。
(※『朱色の地図』は発表時の「鬼のひく地図」を改題したものです)
|
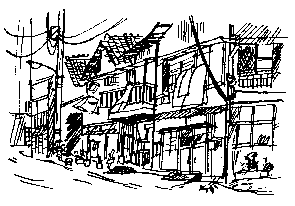 新車で買って半年もたたない朱鴛男(ときお)のバイクだったが、また調子がわるい。
新車で買って半年もたたない朱鴛男(ときお)のバイクだったが、また調子がわるい。