| ●●●●●第1回「冬瓜(とうがん)」●●●●● |
|---|
 |
■最近は都市のスーパーでもよくみかけるようになった。それでも、ここまででかいものが売られているのはまだみたことがない。これは沖縄のおばあがクール宅急便で送ってくれたものである。このくらいのものを料理するとなると、魚のでかいのをさばくのと同じくらいの根性がいる。表面には素手で触るとちくちくする針のような毛がはえているから、やっかいだ。 |
| ■まず西瓜と同じように両端を適当に切り落とす。重いので手がすべって危険だが、まん中からふたつに割る。家族の人数や冷蔵庫の空き、鍋のおおきさなど考慮しつつ、解体。で、これから作るのは「冬瓜の味噌炊き」である。でかい鍋があり、旺盛な食欲の持ち主がそろっていればいっきにかたをつけるのもわるくはない。冬瓜は日持ちのよいものだが割ってしまえば傷むのも早くなる。なるべく新鮮なうちに食べるにこしたことはない。 |  |
| ■わたは捨てない。指先をうまく使って種をとり、ひと茹でしてから一口大に切りそろえ、酢の物にする。身とはちがった歯ごたえの、なかなかおつな菜になるのだ。酸っぱいものがきらいなひとは、だし汁をはって冷やしてから食べてもいいだろう。とにかく自然の恵みを無駄にしないことがあらゆる料理の出発点とこころえたい。 さて、いよいよ「冬瓜の味噌炊き」にとりかかろう。皮をむいた冬瓜をふた口分くらいのおおきさに切る。これは煮崩れを計算にいれてのことである。 |
■豚バラ肉のかたまりをちいさめに切る。量は適当に。タマネギは1個か2個をおおきく切る。ショウガはみじん切りに。この3点をまずいためて鍋にいれる。そこへ朝の味噌汁に使った昆布を放り込む。その鍋に冬瓜をどかどかといれ、水をかぶるくらいに張る。強火にかけて、浮いてきたあくをとっていく。それから、中火にしてしばらく放っておくのである。ストーブがあったらそこへ鍋をかけてのんびり待つなんてのもいい。鍋底がこげないように注意。ときどき水を足して、2時間くらいか。 |
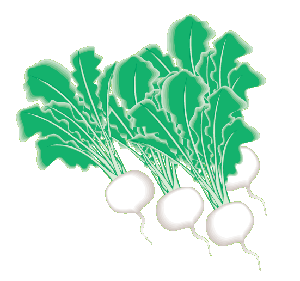 |
■冬瓜がやわらかくなったら、味付けにかかる。味噌をときいれて、鍋のなかのスープが薄い味噌汁程度になるくらいに調節する。子どものいる家庭なら砂糖を加えても良い。砂糖に関してはあんまり神経質にならないほうがいいと思う。酒なり焼酎なりをふりかけ、さらに塩も加えてパンチを利かす。 ごく弱火にしてさらに2時間強おく。鍋底の焦げ付きにはくれぐれも注意する。スープが少なくなり、冬瓜のまわりが煮崩れて飴色になってきたら仕上げである。みりんをたらしてから鍋をあおって全体につやをだす。 |
| ■さて、「冬瓜の味噌炊き」のできあがりだ。この煮崩れてシチューのようになったやつを、炊きたてのごはんにかけてからワイルドにかきこむ。柚子胡椒を友にする。豚肉と味噌と冬瓜の甘味がかなでるハーモニーがなんともいえない。ごはんがいくらあっても足りなくなる。 聞くところによれば、宮中の雑煮は冬瓜の薄切りを使うそうだ。それだけ歴史の旧い食材だということだろう。それなのに、冬瓜が現代の日本人の食卓に登場する場面はさして多くはあるまい。もったいない話だと思う。 |
池波正太郎の『必殺仕掛人』にカブを味噌で煮融かしたものをあついごはんにかけて喰った、という話がある。たしかにあれもうまい。白味噌とカブは絶妙のコンビで、「カブの味噌シチュー」として池波作品には関係なく、すでにわたしのレパートリーにはいっていた。それにしても、冬瓜を味噌で煮た味はカブにまったくひけをとらない。しかも、夏から冬にかけての長いシーズンに渡って出回り、食材として使えるところなど、利点は多い。この料理法に限らず、もっと利用したいものである。 |
| ◆COOKINGのTOPにもどる |